着物の帯の中央に結ばれている「帯締め」。
一見するとおしゃれなアクセントのようにも見えますが、実は着物姿を美しく保つために欠かせない、とても大切な小物なんです。
この記事では、帯締めの役割や種類、TPOに合った使い方から、結び方やお手入れ方法まで、初心者の方にもわかりやすくご紹介します。
- 帯締めの基本的な役割と意味
- 帯締めの種類と使い分け方
- コーディネートのコツ(色・格・場面別)
- 帯締めの結び方とお手入れ方法
帯締めとは?基本の役割と意味

着物を着るとき、「このひもって何のためにあるの?」と思われがちな帯締め。
実は、見た目以上に重要な役割を担っているんです。
まずは帯締めの基本や、どんな働きをしているのかを見ていきましょう。
帯締めってどんなもの?
帯締めは、着物の帯の中央に結ぶひも状の小物です。長さは150cm前後が一般的ですが、長尺タイプで170cm~190cmのものもあります。
見た目の華やかさだけでなく、実用面でも重要な役割を果たしており、着物をきれいに着こなすうえで欠かせない存在です。
帯の形を安定させ、着崩れを防ぐだけでなく、色や素材、結び方によって全体の印象をぐっと引き締めてくれる名脇役でもあります。
帯締めの主な役割
- 帯を固定し、着姿を安定させる
- 帯まわりを引き締めて、バランスよく見せる
- 色や素材でコーディネートに変化をつける
帯揚げがやわらかい印象を添える小物だとすると、帯締めは全体の芯を作るような存在。
小さなパーツながら、着物姿に大きな違いをもたらしてくれます。
帯締めの種類とTPOに合った使い分け
帯締めにはさまざまな種類があり、使われるシーンや着物の格によって適したものが異なります。
ここでは、代表的な帯締めの種類と、それぞれに合う着こなしについてやさしく解説します
| 種類 | 形状・見た目 | 構造・素材 | 印象・特徴 | 主な使用シーン |
|---|---|---|---|---|
| 丸ぐけ | 太くてふっくらした丸筒状 | 布に綿を詰めて縫製 | 華やかでやさしい。装飾性が高く柔らかい | 振袖・訪問着などフォーマルな装いに |
| 平組 | 幅広で平たい帯状 | 組紐(しっかり編まれている) | 安定感があり、もっとも使いやすい定番タイプ | 小紋・色無地・訪問着・留袖・振袖など幅広く対応 |
| 丸組 | 細くて丸い組紐 | 組紐(やわらかめに組まれている) | 軽やかでやさしい印象。柔らかく結びやすい | 小紋・紬・色無地・訪問着・振袖など幅広く対応 |
| 洒落組 | 平組に近いが個性的な色柄や編み模様 | 組紐(装飾性重視のデザイン) | 配色や編み方に個性があり、おしゃれ感を演出できる | カジュアルな街着・アンティーク着物にぴったり |
| 三分紐 | 細くてフラット(幅約9mm) | 組紐(張りのある作り) | 帯留めとセットで使う装飾目的の帯締め。固定力は弱め | 帯留めを使うカジュアルなコーディネートに |
丸ぐけ
丸ぐけは、中に綿が入っていて、ふっくらとした筒状に仕立てられた帯締めです。
布で作られており、組紐ではなく「縫って作る」タイプ。柔らかく、見た目にも華やかな印象を与えます。
振袖や訪問着など、フォーマルな着物にぴったりで、成人式や結婚式などの晴れの日によく使われます。
結んだときにボリュームが出るため、帯まわりを印象的に見せたいときにおすすめです。
丸組
丸組は、丸い断面をした組紐で、平組に比べてやわらかく、やさしい印象を与えます。
シンプルな丸組は細めで軽やかなため、カジュアルな着物にぴったりです。
また、振袖などのフォーマル用の丸組は、ビジューなどの装飾もついていて華やかな印象があります
やわらかく女性らしい印象で、成人式や結婚式などフォーマルな場にぴったりです。
平組
最もベーシックで使いやすい帯締めの定番。
平組は帯にしっかりフィットし、安定感があります。
中には、帯揚げとセットで販売されている商品もあるので、コーディネートに悩む初心者さんにおすすめです。
どちらも訪問着・色無地・小紋・紬など幅広く対応可能で、1本持っていると重宝します。
洒落組(しゃれぐみ)
複雑な編み模様や個性的な配色など、カジュアルな装いにぴったりのデザイン帯締め。
おしゃれ着や街着で、遊び心をプラスしたいときに活躍します。
レースのような夏用の帯締めもあり、おしゃれな季節感を大切にしたい人にもおすすめです!
普段着の着物にちょっとした変化を加えたいときに、ぜひ取り入れてみてください。
三分紐(さんぶひも)
三分紐は帯締めの一種で、特に帯留めとセットで使うための細いひもです。
幅は約9mmと細く、帯留めの裏に通して使う専用の作りになっています。
- 装飾的な目的で使われることが多く、基本はカジュアル向き
- ガラス細工や季節モチーフの帯留めとの組み合わせで、おしゃれの幅が広がる
※三分紐単体では帯の固定力が弱いため、あくまでおしゃれアイテムとしての使い方が主流です。
帯締めの選び方|色・格・素材で印象が変わる

同じ着物でも、帯締めの選び方ひとつで印象ががらりと変わります。
色や素材、着物とのバランスを考えながら、自分らしい1本を見つけるヒントをご紹介します。
着物や帯の格に合わせる
フォーマルな場では、帯締めにも格が求められます。
上品で控えめな色合いのものや、金糸・銀糸入りの帯締めがよく合います。
一方、カジュアルな場面では、柄物やビビッドカラーなど、個性を出せるデザインを自由に選んでOKです。
色合わせのポイント
- 同系色でまとめると、すっきり上品な印象に
- 反対色や濃い色を差し色にすると、コーディネートが引き締まる
帯締めは「帯と着物をつなぐ小物」。全体のバランスを見ながら選ぶと、グッとおしゃれ度が上がります。
帯揚げと色を合わせたり、着物や帯の柄に使われている色を採用するのおすすめです!
素材感にも注目(正絹・化繊など)
- 正絹(しょうけん):やわらかく高級感があり、フォーマルにも対応できる
- 化繊(ポリエステルなど):丈夫でお手入れしやすく、普段使い向き
素材によって、手触りや締め心地も異なります。
まずは手に取って、気に入った一本を見つけてみてくださいね。
帯締めの基本の結び方(貝の口やお太鼓結びで活用)
初心者におすすめなのが「本結び(ほんむすび)」という基本の結び方。結び方は、2回絡げるだけの固結びと同じなのでそこまで難しくありません。
お太鼓結びに合わせて使われることが多く、シンプルで安定感があり、仕上げやすいのが特長です。左右のひもを均等にし、ねじれないようにするのがポイント。
慣れてきたら、「リボン結び」「藤結び」などのアレンジも楽しめます♪
まとめ|帯締めと帯留めで自分らしい着物姿に
帯締めは、着物の着姿を支える実用性と装飾性を兼ね備えた小物です。
種類や結び方、色合わせを少し知っておくだけで、コーディネートの幅がグンと広がります。
さらに三分紐や帯留めを取り入れることで、季節感や自分らしいスタイルを表現することもできますよ。
ぜひ、帯締め選びも楽しみながら、きもののある暮らしをもっと豊かにしていってくださいね。
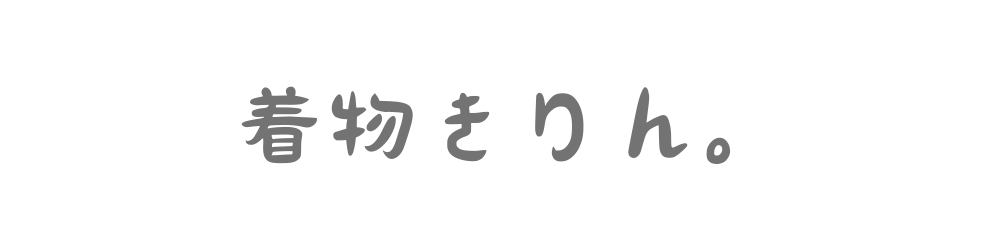




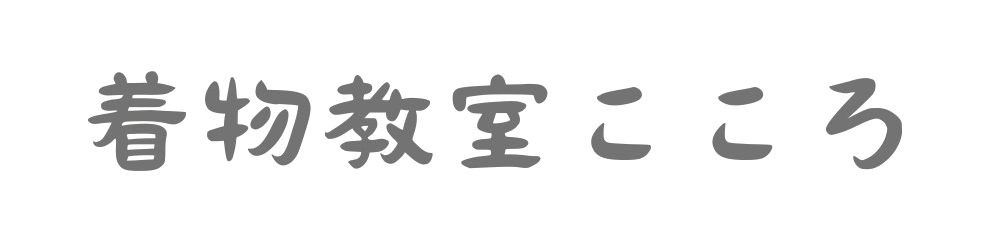
コメント