着物を着るときに欠かせない「長襦袢(ながじゅばん)」。
着物の下に着るもので、直接肌に触れないようにしたり、着崩れを防ぐ役割があります。
この記事では、長襦袢の基本的な役割や種類、選び方、着付けのコツまで、初心者の方にもわかりやすくご紹介。これから着物を楽しみたい方にぴったりの内容です。
長襦袢とは?

長襦袢は、着物の下に着るインナーのような存在です。一見目立たないアイテムですが、実はとても重要な役割を果たしています。
長襦袢の3つの役割
- 肌着としての役目
- 着物を汚さないため
- 着物のシルエットを美しく保つため
長襦袢は、着物を美しく快適に着こなすための必需品です。
まず、肌着としての役目があります。直接肌に触れる「肌襦袢」の上に重ねて着ることで、汗を吸い取り、着物が肌に直接触れるのを防いでくれるのです。そして、長襦袢が間にあることで、着物に汚れが染み込むのを防ぎます。
さらに、着物のシルエットを美しく保つためにも長襦袢は重要です。長襦袢があることで、着物の布が身体にぴったり張り付かず、美しいシルエットを演出できます。衣紋の抜き方や衿元の見せ方にも大きく影響するため、見た目の印象を左右する大切な存在です。
長襦袢の特徴
長襦袢には、着物を着るうえで欠かせないいくつかの特徴があります。
- 着物よりも短い丈の下着
- 衿が付いている(半衿をつけて使用)
- 足元までの長さがある
まず、長襦袢は着物よりもやや短めの丈で仕立てられています。見た目には着物とほとんど同じ長さに見えますが、裾からはみ出ることがないよう、少し短くなっているのがポイントです。
また、衿が付いており、「半衿(はんえり)」をつけて使用するのも特徴のひとつ。半衿は着物から見える白い衿部分となり、清潔感のある印象を与えてくれます。おしゃれな刺繍入りやカラーバリエーションを楽しむ方も増えています。
そして、足元までしっかりと長さがあることで、裾がめくれにくくなり、動いたときにも着崩れしにくいのがメリット。
長襦袢の種類と選び方
長襦袢には、季節や用途に応じてさまざまな種類があります。
季節によって選ぶ長襦袢の種類
春・初夏・初秋・冬向け
一枚仕立ての長襦袢です。夏の暑い時期以外、長く着用できます。真冬には、袖が2枚の無双袖(むそうそで)の長襦袢を選ぶ場合も。
盛夏向け|夏用(絽・麻など)
透け感のある「絽」や通気性の良い「麻」素材で作られた長襦袢。風通しがよく、涼しさを感じられるデザインになっており、7〜8月の真夏にぴったりです。
素材で選ぶ長襦袢
正絹(しょうけん)
上品で滑らかな肌ざわりが特徴。高級感があり、フォーマルな着物にぴったりです。湿気に弱いので、お手入れには注意が必要です。
ポリエステル
自宅で洗えるものが多く、お手入れがしやすいのが魅力。しわになりにくく、普段使いにも◎。初心者の方にも人気です。
麻
夏用に最適な素材。さらっとした肌ざわりと高い通気性が魅力です。汗をかきやすい時期でも快適に着られます。
TPOや使いやすさで選ぶ長襦袢のポイント
二部式襦袢(上下セパレート)
上半身と下半身が分かれているタイプで、着脱が簡単。初心者や着付け練習中の方にも人気があります。
フォーマル用とカジュアル用の違い
結婚式や式典などでは白の無地や正絹を、普段着やお稽古ではカジュアルな色柄付きの襦袢もいいでしょう。
長襦袢の着方と着付けのコツ
長襦袢の着付けの流れ

- 肌襦袢を着る
肌着として、肌襦袢と裾除けなどを着用します。 - 長襦袢を羽織る
背中の中心を合わせ、左右の身頃を整えて前で重ねます。 - 衣紋の抜き加減と腰紐の位置
後ろの衿を少し抜いて衣紋を作り、腰紐でしっかりと固定します。
きれいに着るためのポイント

- 半衿の見せ方
着物から白く美しい半衿が1〜1.5cm程度見えるように整えるのが基本です。 - 背中のシワをのばす
着るときに背中にシワが寄らないよう、引っ張りながら着付けましょう。 - 衣紋を美しく抜く
首の後ろにほどよい抜きを作ることで、うなじが見えて女性らしい着姿になります。
↓15分で長襦袢〜帯結びまで着付けています!
まとめ|長襦袢で着物姿がもっと美しく
長襦袢は、着物の美しさと快適さを支える大切なアイテム。着物と肌の間で見えないサポートをしてくれる存在です。
初心者の方も、まずは扱いやすい素材や二部式からスタートして、少しずつ着物の楽しみを広げていきましょう。
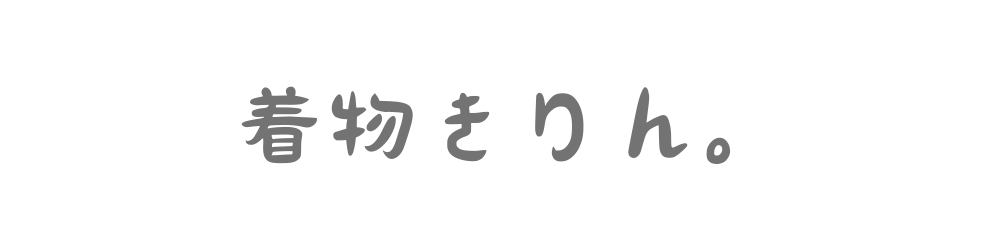



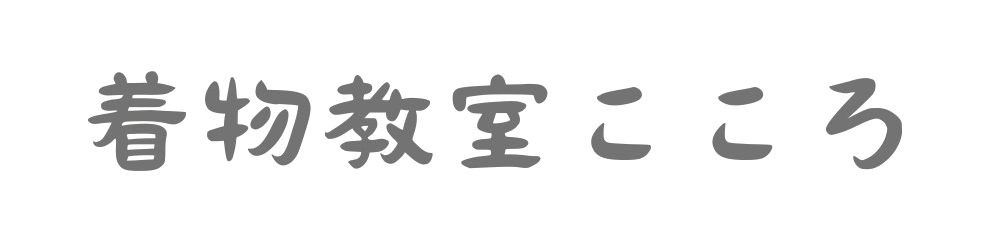
コメント